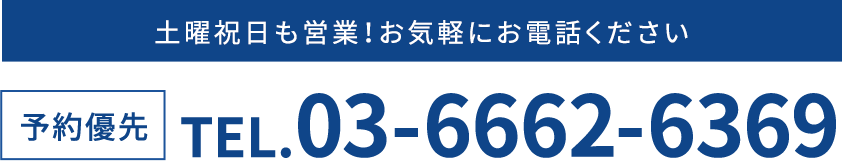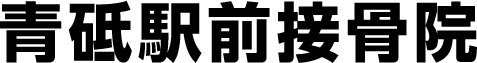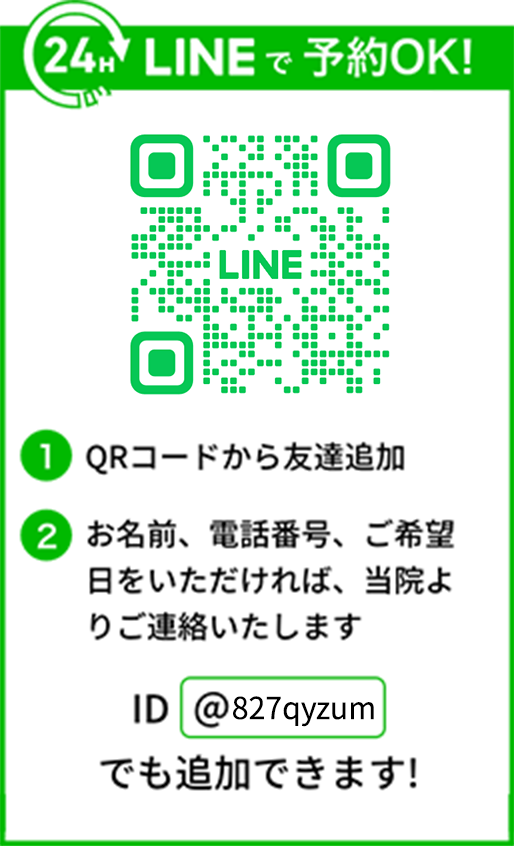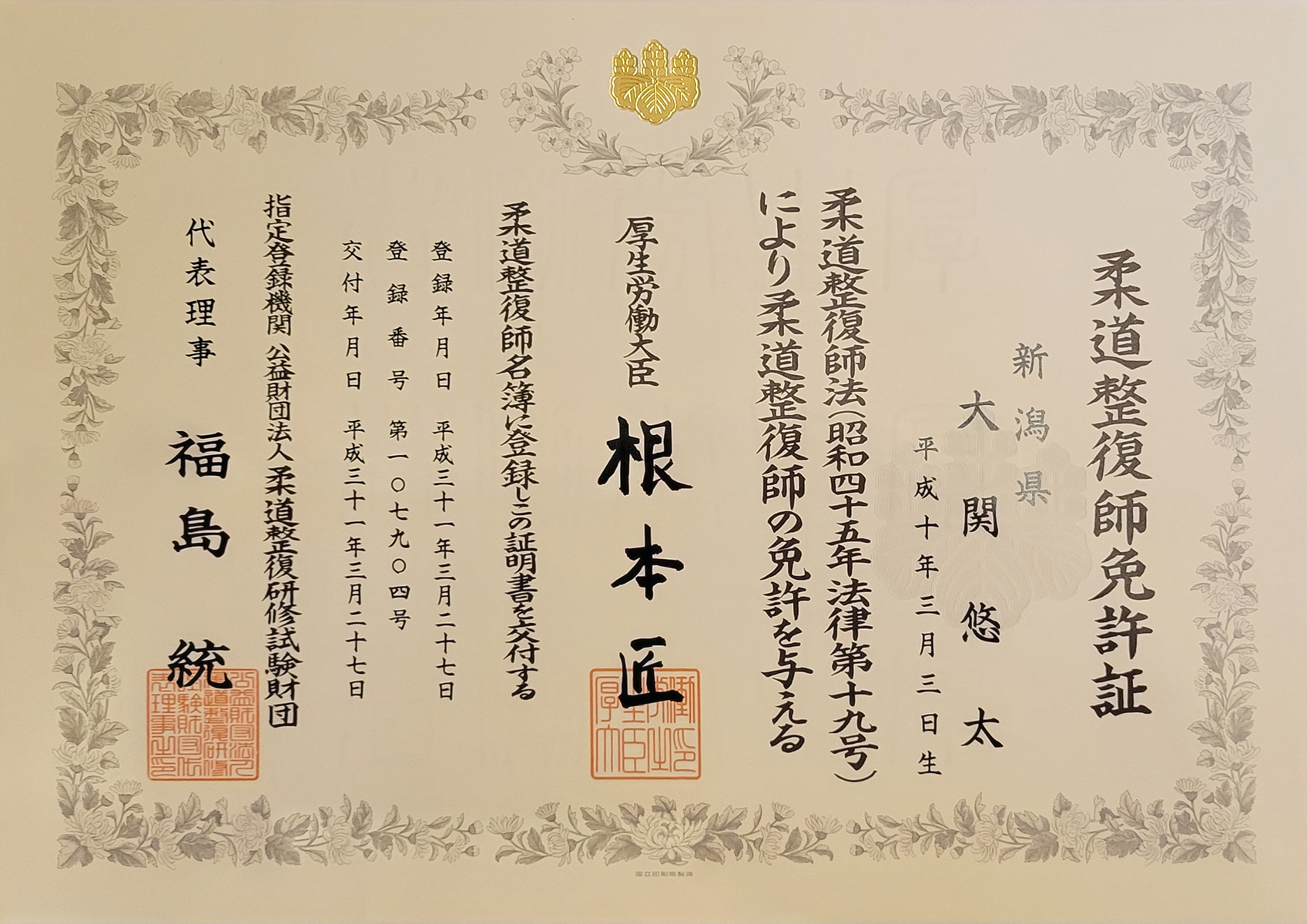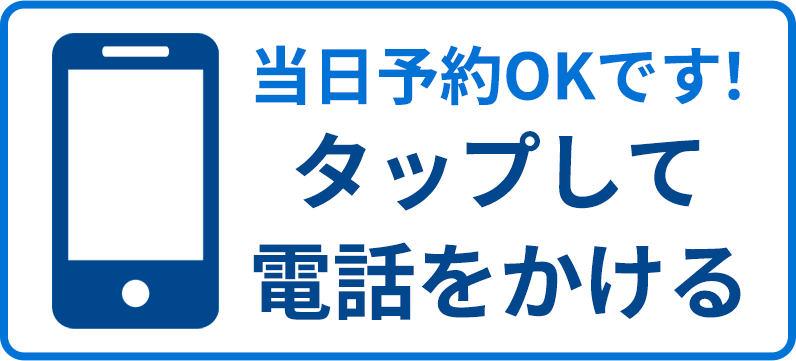足底腱膜炎について
足底腱膜炎とは
足底腱膜炎とは、足底腱膜が炎症を起こし、痛みが生じる疾患のことです。足の裏には、かかとからそれぞれの指の付け根へと及ぶ靭帯性の「腱」が膜のように広がっており、この膜のことを「足底腱膜」と呼んでいます。
足底腱膜炎の原因
ふくらはぎやアキレス腱が硬い人、足を引き上げる力が弱い人、スポーツや激しい運動で過度な負担をかける人、足の裏のアーチが崩れている人に加えて、加齢や肥満でも、足を踏み返すときに足底腱膜にかかる負担が大きくなり、足底腱膜炎になってしまいます。通常、かかとからふくらはぎの筋肉やアキレス腱が柔軟である場合、痛みは出ません。
10~20代の若年層に多いのが、激しいスポーツや運動を繰り返し行うことで足の裏に強い衝撃を受けて足底腱膜がダメージを受けることです。マラソンやジョギングなどを長距離で、特にアスファルト舗装された硬い道を走っているときは注意しましょう。長時間の立ち仕事も疲労の蓄積によって足底腱膜への負荷が大きくなります。高齢者は老化によって足底腱膜の線維が弱くなるため、激しい運動をしていなくても足底腱膜炎になる傾向があります。肥満も足にかかる負担が大きいことから、足の裏に強い衝撃がかかるような運動はできるだけ注意することを心がけましょう。
また、足のアーチの構造が崩れている場合は足底腱膜炎にかかりやすい傾向があります。例えば、アーチが低い(扁平足)人が該当します。アーチが下がってしまう足は、足底腱膜の起始部である踵骨(しょうこつ)に大きな負荷がかかります。ほかにも、ヒールのある靴を履くのが楽な人は、アキレス腱が硬いことの裏返しであり、かかとに重心がかかりがちです。気づかないうちに足首が硬くなって、前傾姿勢を取れなくなってしまいます。サイズが合わない靴を履き続けるのも足底腱膜炎を誘発するので注意が必要です。
足底腱膜炎のセルフケア
足底腱膜炎は、歩行時や運動時に足底腱膜にかかる負担を軽減すること、足首や足、ふくらはぎの筋肉を柔軟に保つことが大切です。足が地面に接するときの衝撃を吸収できるようなクッション性の高い靴を履く、自分に合ったインソールを靴に入れるといった予防をすることで、足底腱膜への負担が軽減できます。足首や足、ふくらはぎの筋肉を柔軟に保つために、アキレス腱を気持ちよく伸ばすストレッチや足底腱膜の疲労解消のためのマッサージも効果的です。ストレッチを行うタイミングは朝起きたときや、たくさん走ったり歩いたりした後、お風呂上がりなどが良いでしょう。
・アキレス腱ストレッチ
片方の足を後ろに下げ、前に出ている足のひざをゆっくり曲げていきます。伸ばした足のアキレス腱がしっかり伸びるのを感じながら30~60秒程度キープ。足を入れ替えて反対側も同様に行います。1日2~3回を目安にして、アキレス腱を意識しながら行いましょう。
・ふくらはぎのストレッチ
痛みがあるほうの足を後ろに大きく引きます。そのときに、かかとはしっかり床に付けましょう。前に出している足の膝に両手をのせて、ゆっくりと重心を前に出している足に移動させます。足を入れ替えて反対側も同様に行います。1日2~3回行うと良いでしょう。重心を移動させるときは、ふくらはぎを意識しながら行いましょう。
・テニスボールを使ったストレッチ
椅子に座って、土踏まずの部分でテニスボールを転がすようにしてストレッチします。3分×3回行います。足を入れ替えて反対側も同様に行います。
・足底腱膜ストレッチ
床に座ってストレッチするほうの足のひざを立てます。片方の手で足指をゆっくり反らせながら、もう片方の手のひらで足の裏をよくもみほぐします。反対側の足も同様に行います。